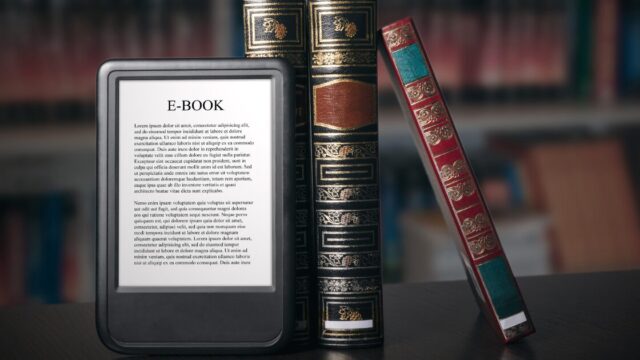多くの人が悩んでいるので、今回はその解決策についてお話しします。
今の経済政策って、なんだか現実とズレていると思ったことはありませんか?実はその根本には、「主流派経済学」という理論の問題があるんです。
主流派経済学の最大の特徴は、驚くほど非現実的な前提からスタートしていること。たとえば、「経済合理性だけで動く人(経済人)が、同じ情報を持って自由に取引を行うと、すべての需要と供給が一致して、満足度(効用)が最大化される」という理屈。これは“一般均衡理論”という仮説ですが、現実の世界とはかけ離れた空想にすぎません。
たとえばこの理論では、「貨幣(お金)」が登場しない。なんと“物々交換”の世界を前提にしているのです。また、自由貿易を正当化する「比較優位の理論」も、「世界には国が2つ、財(商品)が2種類、生産要素は労働だけ」というような、まるでおとぎ話のような条件を前提にしています。
でも現実の経済は、そんなに単純じゃありません。実際には、「銀行が企業にお金を貸すかどうか」「企業が投資するかどうか」「その投資でどれだけ生産性が上がるか」――どれも事前には誰にもわからないのです。
さらに、主流派経済学は「政府」の存在も軽視します。政府が財政支出を増やしたり減らしたり、増税や減税を決めたりすることは、市場の自由な競争とは対極にあるとされるため、理論の中では排除されがちです。
しかし、現実の経済では、企業が銀行から資金を借りて投資し、生産性を高める――そんな流れが経済成長のカギになります。この重要なサイクルを無視してしまう主流派経済学では、当然、正確な政策判断などできるはずがありません。
なぜこのような理論が今も使われているのでしょうか?それは、「数式でキレイにモデル化できるから」。でも実際には、不確定要素が多すぎて、モデルにしても予測はほとんど外れてしまいます。
現実の経済は、人の感情や予測不能な出来事、そしてお金の流れが複雑に絡み合って動いています。数式ではとても追いつけないんです。
このように非現実的な理論に基づいて政策を続けてきた結果、日本経済は今や大きな停滞に直面しています。そろそろ「机上の空論」から卒業して、現実に目を向けた新しい経済の考え方を取り入れるべき時ではないでしょうか。
この情報が皆さんのお役に立てば幸いです。